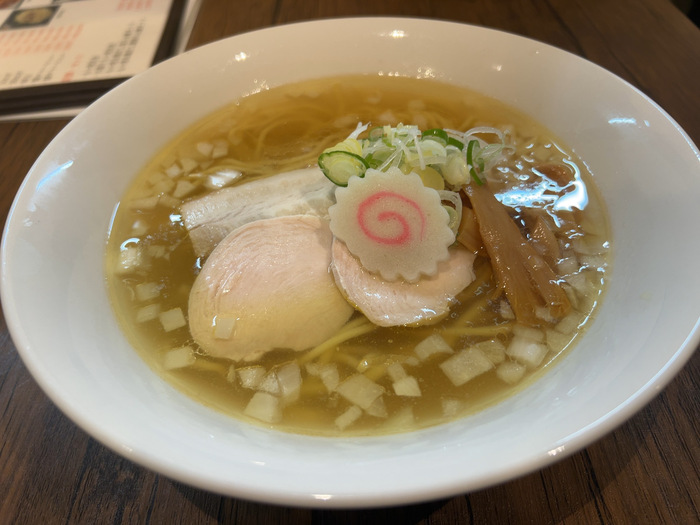【FP監修】子供のための積立~定期預金、保険、投資、おすすめの方法はどれ?

子供の将来のための貯蓄は、お母さん、お父さんにとって避けては通れない問題ですよね。
ベビー用品メーカーのコンビタウンの調査によると、子供のための貯蓄を行っている家庭は全体の75%という結果が出ています。
また、貯蓄方法としては学資保険と普通預金が圧倒的に多く、次に定期預金や生命保険、投資信託などが続きます。
今回の記事では子供のための貯金は最低でもいくら必要で、どんな方法がおすすめなのかについて詳しく解説します。
今の貯蓄方法を見直す参考にしてください。
出典:コンビタウン公式サイト
子供の貯金の目標額はいくらがいい?
カードローン情報メディア「ワイズローン」による「貯金実態調査2019」では、子供のための貯金額の平均は368万円という結果が出ています。
また、口コミ情報サイト「コンビタウン」が行ったアンケートによると、子供が18歳になるまでに貯めておきたい目標貯金額は「400万~500万円」という回答が一番多いことがわかりました。
子供のための貯金の中でも一番多くの割合を占めるのはやはり教育資金です。
では、実際に子供一人当たりの教育資金はいくら必要なのでしょうか?
まず小学校から高校まで全て公立の学校に通った場合で、総額約125万円。
全て私立の学校に通った場合は約390万円の学費が必要と言われています。
次に大学進学にかかる費用は下記の通りです。
| 入学時費用 | 在学費用 | 総額 | |
| 国公立 | 80万1千円 | 459万2千円 | 539万3千円 |
| 私立 文系 |
90万4千円 | 640万4千円 | 730万8千円 |
| 私立 理系 |
85万5千円 | 741万2千円 | 826万7千円 |
上記のように、子どもの教育費の中でも、最もお金がかかるのが大学費用で、特に大学進学の初年度は受験料や入学金などの入学費用と授業料や通学費などの在学費用がかかります。
したがって大学初年度までに入学費用と在学費用を用意しておくためには、少なくとも200万~300万円は蓄えておく必要があるということです。
出典:ワイズローン「貯金実態調査2019」
月々いくらずつ貯金するべき?
子供の教育費の中でも、大学進学時に一番まとまったお金が必要ということが分かりました。
公立か私立のどちらに通うのかによっても必要な金額は変わってきますが、設定した目標金額に応じて月々の貯金額を決めていくようにしましょう。
例えば「子供が18歳になるまでに200万円を貯める」と決めた場合、子供が0歳から貯金を始めるとすると1年間に約11万円、月々約1万円となります。
仮に500万円を目標とした場合は1年間で約28万円、月々約2万3千円の貯金が必要です。
これらの金額を毎日の生活費や養育費、高校までの教育費とは別に貯めていく必要があるので、簡単なことではありませんよね。
コンビタウンによる調査で「子供のための貯金は具体的にどこから回しているのか?」というアンケートでは、「給料」が一番多く、次いで「お年玉、お小遣い」「児童手当、子供手当」という回答が多く集まっています。
中でも児童手当は子供1人あたり月に1万~1万5千円が支給されるので、これを使わずにそのまま子供のための貯金として回すようにすることはとてもおすすめの方法です。
仮に1万円以上の貯蓄が難しいといった場合でも、月々5千円を18年間貯めると約100万円の貯蓄ができます。
大学入学に充分な金額では無いにしても、確実に教育費の足しにすることはできるので、少額ずつでも毎月決まった金額を積立てるようにしましょう。
子供のための積立方法でおすすめなのは?
教育費を貯めるための貯蓄方法はいくつかありますが、圧倒的に利用者が多いのは学資保険と普通預金、次いで生命保険や投資信託と続きます。
そしてそれぞれにメリット・デメリットがあります。
ここからはそれぞれの貯蓄方法について解説します。
銀行の普通預金や定期預金を利用して積立てる方法
1番労力がいらずにサッとできる方法は銀行で普通預金や定期預金を利用して積み立てる方法ではないでしょうか。
最近では銀行の金利が大幅に下がってしまっているので、「お金を増やす」という点では難しいですが、家計の状況に応じて貯金額を変えたり、また引き出しが簡単にできるなど、資金の流動性が高いところはメリットとして挙げられます。
逆に簡単に引き出せるので、意志が弱いとなかなか目標額にたどり着かないということがデメリットでもあります。
例えば生活費と区別するため子ども名義の銀行口座を開設して、そこに毎月定額を振り込むように設定すれば、ふと使ってしまうという事態も防ぎやすくなります。
ゆうちょ銀行では0歳児の口座開設に限りお祝い金をもらえるなど、キャンペーンを行っている期間もあります。
こういったキャンペーンをうまく利用できるといいですね。
ただし子供名義の口座開設には注意も必要です。
子供名義の口座を作る際は贈与税に注意
子供の名義で口座を作ったとしても、赤ちゃんや子供が小さい頃は、必然的に親がキャッシュカードや通帳を管理することになります。
例え子ども名義の口座であっても、本人が自由に利用できない場合は、実際の預金者である親の名義預金とみなされます。
贈与税は現在年間110万円を超えた時点で発生しますが、親が毎年子供の口座に入金しても、親の名義預金の場合だと贈与として認められません。
結果、子供が成人した時に仮に200万円が貯まっていたとすると、その口座を渡した時点でその金額が贈与としてみなされる事になるのです。
しかし、親から子へ渡したお金すべてが贈与税の対象という訳ではなく、社会通念上認められる範囲であれば、生活費や教育費に関するお金の移動は贈与に当たらず非課税となります。
もちろん、名目上は生活費や教育費として、実質的に生活費や教育費に直接充てない場合は贈与にあたります。
ですので、どうしてもそれ以外の用途に使わせたいという時は、この場合200万円を一気に渡すのではなく、非課税の枠で数年毎に分けて渡すという方が良いでしょう。
学資保険や終身保険で積立てる方法
学資保険とは子どもの教育資金を貯めるのに適した貯蓄性の保険商品のことで、終身保険とは、その名の通り生涯に渡って保障が継続する保険商品のこと。
こういった保険を利用して積立てる人たちもたくさんいます。
保険で積み立てる場合のメリットは、銀行での預貯金と違って毎月の積立額に生命保険料控除が適用され、節税対策ができるという点が挙げられます。
学資保険の生命保険料控除について詳しくはこちら⇓
学資保険を利用する方法
学資保険は教育資金を貯める方法の代表的な存在です。
毎月決まった金額を保険料として積み立てておくことで、子どもの大学や高校入学時に学資金や満期受取金として受け取ることができます。
学資保険のメリットは、
- 計画的に教育費用を積み立てることができる
- 払い込んだ金額よりも多くの学資金を受け取れることがある
- 親に万が一のことがあった場合でも保険料の払込が免除される
の3つが挙げられます。
学資保険に加入すると、毎月決まった金額が自動的に銀行口座から引き落とされます。
原則的に途中で積み立てたお金を引き出せない為、お金を貯める意思が弱くてもコツコツと貯金をしていくことができます。
また、返戻率の高い学資保険を選ぶと、払った金額よりも多い金額の学資金を受け取ることができます。
返戻率とは、支払った保険料の総額に対する、受け取れる金額の総額の割合のことで、100%を超えれば支払額より多くの学資金を受け取ることができます。
そして学資保険の最大のメリットは、契約者である保護者が万が一の状態になった場合、支払いが免除される払込免除特約がついているところ。
長い人生、何が起こるかわからないとはいえ、子どもの将来に負担をかけたくないのが親心というもの。
学資保険はお金を積み立てるだけではなく、いざというときのための安心感もついてきます。
反対に学資保険にもデメリットはあります。
具体的には
- 途中解約すると元本割れを起こしてしまう
- 保障型の学資保険は返戻率が100%を割ることがある
途中で学資保険を解約した場合、ほとんどが元本割れをしてしまうことがデメリットと言えます。
解約という結論にいたるには様々な事情があるでしょうが、途中解約は確実に受け取る金額が少なくなります。
もう一つ、保障型の学資保険に加入した場合は満期を迎えたとしても受け取る金額が少なくなることがあります。
育英年金や死亡保険金、医療保障など受け取れる保障が充実しているので、その分返戻率が低くなっているのです。
純粋に学資保険で受け取れる金額を増やしたいのであれば、シンプルな「貯蓄型」の学資保険がいいですね。
どの保険会社の貯蓄型学資保険であっても、払込免除特約がついているものがほとんどです。
あわせて読みたい。
終身保険を利用する場合
最近では、学資保険の代わりに終身保険で子どもの教育費を貯蓄する家庭も増えてきています。
本来は被保険者が亡くなったり、高度障害状態になった場合に保険金が支払われる種類の保険ですが、学資保険の代わりに利用する人も増えています。
主なメリットは次のとおりです。
- 貯蓄性が高く解約返戻金を受け取れる
- もちろん保障は一生涯
- 払込期間に柔軟性がある
終身保険は、お金が必要な時に解約すると解約返戻金を受け取ることができます。
ある程度の期間払込を続けていると、解約返戻金が元本の100%を超えて、その後も年月が立つにつれてどんどんアップし続けるのです。
この解約返戻金を、学費に充てることができます。
もちろん解約しなければ保障は一生涯続きますし、払込期間もいろいろ設定できます。
払込期間は、一生涯に渡って払い続ける「終身払い」と契約したときから10年ですべて払い込んでしまう「有期払い」を選ぶことができます。10年の他にも15年や20年で払い込むタイプがありますし、払い込んだあとはもちろん保険料の負担はありません。
今度は終身保険のデメリットを見ていきます。
終身保険は基本的には学費のための保険ではなく契約者に万が一のことがあったときに保障をするもの。
死亡保障がついている分、学資保険よりも月々の保険料が高くなってしまうことが挙げられます。
また、保険料を振り込んでいる期間が短い状態で途中解約した場合は元本割れする可能性が高いこともデメリットとしてあります。
保険料の支払いが高くても、万が一の場合の保障もほしいという方には終身保険はオススメです。
ジュニアNISAなどの投資商品を利用する方法
教育費用を投資商品で貯めていく方法もあります。
ジュニアNISAは正式名称を「未成年者少額投資非課税制度」と言います。
日本在住の0歳から19歳までの未成年者の名義で口座が開設でき、年間80万円までの投資枠があります。
最大のメリットは、年間で80万円(最長で5年のため最大400万円)の投資枠で得た利益や配当金が非課税であることがあげられます。
ただし2023年にはジュニアNISAは終了してしまうため、興味があるなら早めに口座開設をしたほうがいいですね。
運用益(儲けることができたお金)に税金がかからないので、運用がうまく行けば普通預金や学資保険よりも高い利回りでお金を増やしていくことができます。
デメリットとしては、子どもが18歳になるまで原則払い出しができないことと、投資商品なのでお金が必要となる時期の相場によってはもちろん元本割れの危険性があるということです。
したがって、投資商品だけで教育資金を積み立てるのにはリターンもあればその分リスクがあるのはきちんと把握しておかなくてはいけません。
子供のための積立方法一覧
| メリット | デメリット | |
| 銀行での 預金 |
状況に応じて柔軟に入出金が可能。 | 金利が低い為、あまり増やすことができない。 贈与税がかかる場合がある。 |
| 学資 保険 |
積立てた金額より多くを受け取れる。 払込免除特約がついている。 生命保険料控除が適用される。 |
途中で引き出すことができない。 解約すると元本割れする。 |
| 終身 保険 |
一生涯の保障が得られる。 生命保険料控除が適用される。 |
保障が手厚い分、支払い保険料が高くなりがち。 |
| 投資 信託 |
運用がうまくいけば、お金をかなり増やすことができる。 | 元本割れするリスクがある。 |
まとめ

今回は、子供のために目標とすべき貯金額や、貯金方法について解説しました。
子供が進みたい道を応援してあげるためには、やはりそのためのお金が必要不可欠です。
少ない金額では無いので、早い時期から無理のない範囲で少しずつ積立てていくことで、必要な時に必要なお金を用意することができます。
また貯蓄方法には様々なものがあり、家計によっても変わってきます。
色々な方法を比較し、一番合った方法で納得して貯金していくようにしましょう。
|